冷笑にみちた、いまの社会の温度を、もっとあたたかくアゲたい。
そう思い、シンポジウムの企画意図としては、次のような狙いがありました。
いつも「市民運動に参加している」という人だけではなく、「市民連合ふくおかに、直接関わっていないけど想いは共有してる」というような人や、また「参加するにはハードルを感じて…」と思う人、また「過去に市民運動へ関わった事があった」という方、様々な人たちにインタビュー協力してもらいました。そこで「少し離れているからこそ見える部分」を集めて、未来を考えるヒントになれば、という狙いです。
まずシンポジウムのスタートとして、福岡県選挙管理委員会非公認キャラクターの「とうヒョウくん」と、三苫哲也さんによる、漫才でのオープニングでした。その漫才の内容にも絡んだ、3つの質問で構成された街頭インタビュー動画を、会場のみなさんと一緒に見ました。その質問とは、以下の3つです。
Q1. 政治とお金のこと
税金の透明性ランキング(世界租税支出透明性指数)世界104カ国中で日本は94位。裏金・脱税など、政治とお金についてどう思う?
Q2. 声を上げること
韓国では市民の力で大統領を変えることもある。デモや声を上げることについて、どう思う?
Q3. 選挙について
なぜ投票率が低いのですか?投票率を上げるには?選挙で社会が変わる?そもそも投票率をあげた方がいいの?
3人のパネリストのお一人目、あやめさん。大正時代のお祖母さまの着物をまとっての登場です。彼女は小さいお子さんをお二人を抱えながら、行政書士をされています。市民連合ふくおか主催の「街角トークライブ」のとうヒョウくんコント動画を観ていたあやめさんに、お子さんたちが横から覗いてきて「お母さんがいつも言ってることやん~」と言われたエピソードも、自己紹介として披露してくださいました。そういった子育てをされる母親と生活者からの視点で、教育分野などの発言も飛び出します。行政書士という仕事柄なのでしょうか、保守的な考えの方が多く、意見を言ったり行動しても、全く反応がない事が多いとおっしゃいます。
そういった事もあり「政治的社会的な話を人前で話すのは初めてで緊張する」と言われていましたが、堂々たるコメントぶりでした。
パネルディスカッションの締めくくりでは、イタリアの作家・ジャンニ・ロダーリの言葉を、大井さんは引用されました。
「みんなに本を読んでもらいたい。文学者や詩人になるためではない。もう誰も奴隷にならないために」
深い言葉です。そのためには、僕たちひとりひとりが考え続けることに鍵があるのでしょう。
パネリストの3人目、出水薫先生。定期的に会合で同席しているという大井さんが「あんなエネルギッシュな出水さんを初めてみた」と感嘆させられるほど、キレッキレなトークでした。
実は、今回のシンポジウムの最後に、虚実が交差する仕掛けを僕はやってみました。まぁ、このオチをやりたくてパネルディスカッション形式をやってみたという下心があったのですが。
その時に「自分の立ち位置を揺るがすような議論をやりたい~」という旨の言葉を僕は使ったのですが、まさに、僕が設定した質問自体を問い返すような発言が、出水先生から何度も刃のように発せられました。流石ですね。
そして、トーク中には、以下のような興味深い本をたくさん紹介していただきました。
斉藤真理子著、イーストプレス
諸富徹著、筑摩書房
朴沙羅(パク・サラ)著、ちくま文庫
将基面貴巳著、ちくまプリマー新書
とにかく、企画担当者としては時間内に終わらせることが使命。ですので、始まる前は不安だらけでしたが、パネリストの御三人と進行役の三苫さんの手腕で、無事に時間内に終えることが出来、濃厚な時間を作ることが出来たと思います。そして、再確認したのは、出水先生から話された言葉「このシンポジウムは答え、正解がでない対話」という趣旨の発言が、今回のイベントの意味や、市民連合ふくおかの活動自体を物語っているのだろうということ。きっと、みなさんからの感想は様々だと思いますが、いま現段階の僕からの投げかけは、最適解かなと想像しています。
おそらくですが「深刻な政治状況に、漫才や歌や踊りのパフォーマンスなんて不謹慎だ。深刻さが足りない」だなんて、違和感を感じた参加者もたくさんいたのでは…と想像します。そうかもしれません。
でも、誰かが傷つくばかりで、暗くなってしまうような罵詈雑言で怒声が飛び交うような世界を、僕は笑い飛ばしたいのです。そう思って企画しました。
さて、社会の温度はアガったのでしょうか?
ご協力、ご参加された方々、ありがとうございました。
(文責 いのうえしんぢ)




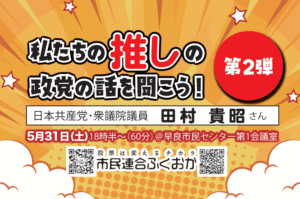

コメント